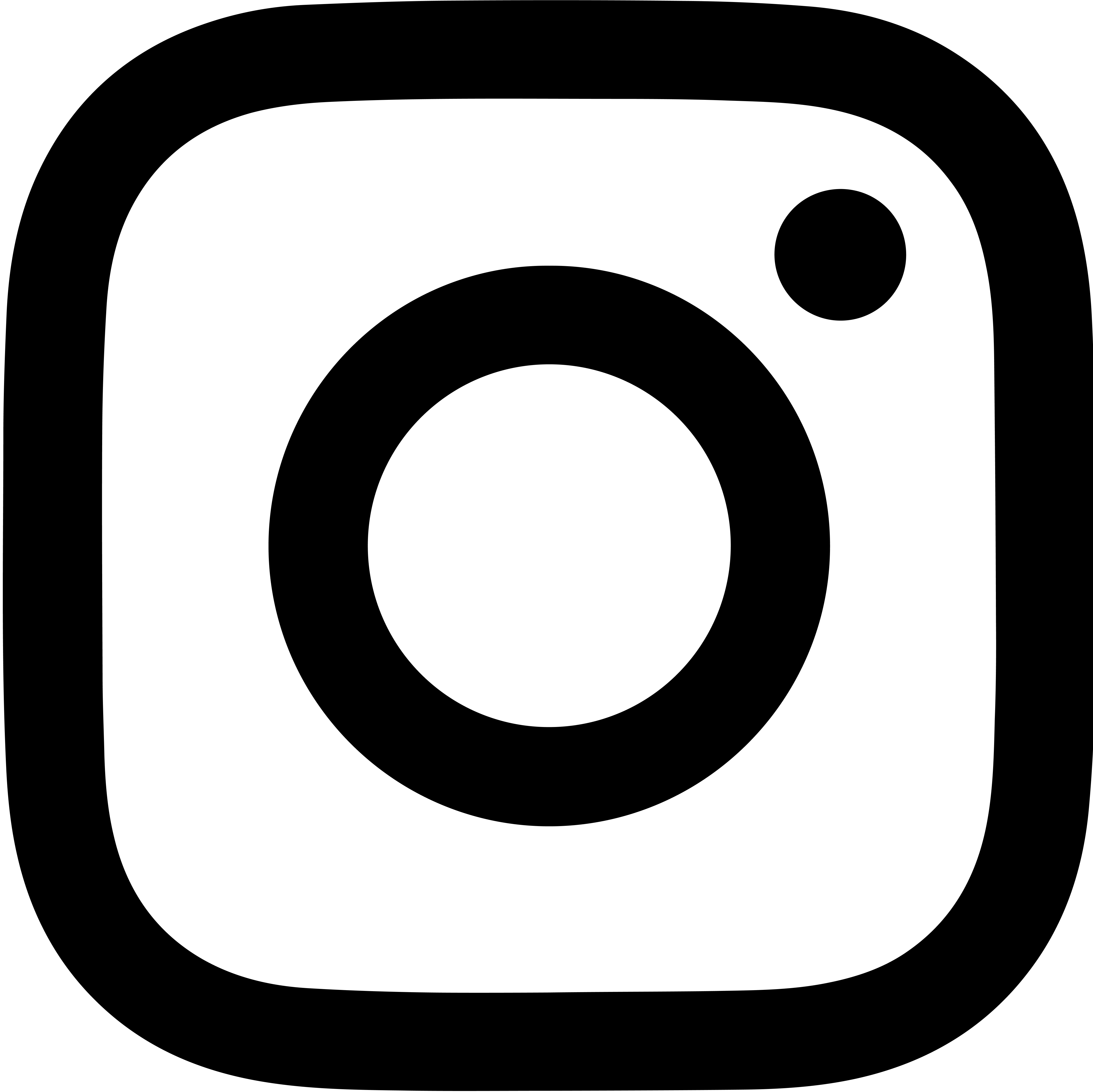Q1
小学校の統合再編について伺います。小学校6校を1校に統合再編する計画が進んでいます。少子化、教育の充実、児童生徒の安全について、
どのように取り組みますか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
少子化による学校規模の適正化、将来を担う子どもたちのより良い教育環境の構築に向け、令和元年度から小学校の統合再編に取り組んできました。
統合再編をすることで、統合小学校の児童数が増え、多様な考え方に触れ、切磋琢磨することを通して、社会性や協調性、たくましさが育みやすくなる環境となります。
また、教職員の増加が見込まれ、経験、教科、専門性など、バランスのとれた教員の配置が可能となり、教育環境の充実と教育の質の向上が図られます。
そして、統合小学校の開校後、小学生は、中学生と同一の敷地で学校生活を送ることとなります。
通学については、徒歩及びスクールバスを想定しているため、児童の安全対策が最優先課題であります。
中学校敷地の周辺道路については、できる限り歩車分離を図る計画とし、また通学路については、関係機関と連携を図り、安全対策に努めてまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q2
学校給食費の無償化を国で検討していることについて伺います。
町の学校給食はおいしいと評判で すが、国負担分の範囲に経費を収めるため、
給食の質が下がるのではと不安の声が聞かれます。学校給食にどのように取り組みますか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
ふるさと納税を活用して、高校卒業までの子から数えて3人目以降の児童生徒の給食費の無償化に令和6年度から取り組んでいます。
学校給食の無償化については、国が令和8年度から小学校で、その後に中学校にも広げるという報道は認識しています。しかしながら、その無償化の詳細については、明らかになっていません。
物価高騰等を理由に給食費を増額している自治体がある中、町では、令和4年度から食材費の高騰分を町が負担することにより保護者負担の軽減を図り、値上げすることなく、また給食の質を落とすことなく、おいしい学校給食を提供し続けています。
今後も、給食の質を維持しながら、安全で安心なおいしい給食の提供に努めてまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q3
小中学校の不登校に悩む子どもが増えています。町独自の取り組みを行う考えはありますか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
不登校は、問題行動ではないとされていますが、児童生徒の社会的自立を目指して、
町内の学校では、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関等との連携を強化し、
教育相談体制を充実するなど、児童生徒一人一人に寄り添った支援を行っています。
また、令和6年4月には、旧町立図書館を改修した「こども家庭センター」を開設しています。
施設内には、こどもの居場所や子育てサロンのほか、一時預かりスペースも設置し、こどもや子育て世帯が抱える様々な課題に寄り添い、包括的な支援を実施しています。
こどもの居場所では、学習・生活支援に加え、多様な体験活動、不登校児童生徒の保護者を対象にした講演や座談会等を実施し、これらの交流を通じて、こどもたちの将来の自立に向けた活動を展開しています。
今後においても、不登校対策に取り組んでまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q4
小学校の統合再編後、旧小学校6校の校舎と体育館をどのように活用したい考えですか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
各小学校は、防災施設及び地域コミュニティの場として活用されてきました。
現在、各小学校の体育館は、洪水以外の災害時の避難所として指定されており、平時においては、校庭も含め、生涯スポーツ活動の場として利用されています。
統合後の利活用ですが、体育館については、災害時の指定避難所や生涯スポーツ活動の場であることから、引き続き、維持管理していくとともに、近年の猛暑を考慮し、空調設備の設置について検討してまいります。
校舎については、昭和40年代から50年代に建設されたものが多くあり、老朽化への対応が課題となっています。
町の学校敷地の多くは、利活用しやすい市街化区域ではなく、市街化調整区域となっています。
この市街化調整区域は、都市計画法をはじめ様々な法的な制限を受けることから、総合的に判断した上で、一部の校舎を除き順次解体を進めてまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q5
ごみ処理について伺います。新たなごみ処理施設を鴻巣市に建設する計画が進んでいます。
どのように取り組みますか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
新たなごみ処理施設等整備事業については、令和3年度に鴻巣市、北本市及び吉見町の2市1町で締結した基本合意書の下、
令和4年度に埼玉中部環境保全組合で事務を開始しました。
令和6年度には「新たなごみ処理施設等整備基本計画」が策定され、令和14年度からの施設の稼働開始が予定されています。
ごみの処理は、町民生活に欠かすことのできない重要な事業であるので、埼玉中部環境保全組合及び組合を構成する鴻巣市及び北本市と連携し、鋭意取り組んでまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q6
水道について伺います。水道料金が昨秋、値上げされました。
近い将来、さらなる値上げも検討されているようです。どのような対策を検討していますか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
施設の耐震化に要する費用の確保、電気料金や燃料価格などの高騰に伴う維持管理費の増大、
さらには、町の水道水は100%県水を利用しているため、その供給元である県営水道の値上げに対応するため、
令和6年10月から水道料金を値上げさせていただきました。
値上げ幅の算定にあたっては、令和10年度までの工事費、維持管理費など様々な収入・支出について想定し、
財政シミュレーションをしていますので、大規模災害の発生や劇的な環境の変化が起こらない限り、
令和10年度までに値上げを行う予定はありません。
今後においても、水道インフラの適正な維持管理に努めてまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q7
災害時の避難について伺います。能登半島地震のとき、避難所に行くことが困難な人が自宅近くで 自主避難したという事例が数多くありました。
単身高齢者、ペットを飼っているなど、自主避難と いう形に町はどのように対応する考えですか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
令和6年能登半島地震では、自治体が指定した避難所以外の施設である近所のビニールハウスや集会所など、
いわゆる「自主避難所」に避難した方が多かったと聞いています。
災害時には、町においても自主避難所に避難した方の情報を得ることが困難なことから、
自主防災組織と連携し、日頃から、それぞれの地域に災害時要配慮者や自宅でペットを飼っているために避難行動を取りづらい方がどの程度いるかなど、
スムーズな状況把握を可能とする体制づくりを進め、自主避難者の支援に努めてまいります。
大規模災害が発生した場合、公助(公的機関による援助や救助)の機能には限界があります。
被害を最小限に抑えるには、自助(命や財産を守るため、自分や家族で防災に取り組むこと)
・共助(近所や地域の方々と助け合うこと)・公助の3つで取り組むことが重要となります。
今後においても、自助、共助の重要性を周知啓発するとともに、共助の中心的な役割を担うことが期待されている自主防災組織の支援に努めてまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q8
ごみ出しが困難な世帯のごみに対し、令和7年度から東松山市は戸別収集に取り組み始めます。
自治体の経費負担は増えます。町民から要望が出た場合、どのように対応しますか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
現在、町では、戸別のゴミ出し支援は行っていませんが、
吉見町社会福祉協議会が実施している「ささえあいサービス事業」の取組の一つである「ごみ出しサービス」について、ご案内しています。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q9
デマンド型交通が昨年3台に増えたものの、交通弱者にとってまだ不便といわれます。
さらなる利便性向上にどう取り組みますか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
現在乗り入れを行っている町外の病院4か所及び大型商業施設3か所については、
路線バス及び巡回バスの利用者アンケートや懇談会等を通じて把握した町民ニーズ、
通院する方が多い医療機関などの基礎的データに加えて、普通自動車第2種免許を保有する旅客ドライバーの全国的な減少傾向なども踏まえ、
町の後期高齢者数がピークを迎える時期においても持続可能な仕組みとすることを念頭に検討を重ね決定したものです。
さらなる利便性向上については、高齢化が進行する中でも、
誰もが自宅近くで乗り降りできるサービスを将来にわたって安定的に確保していく持続可能性と合わせ取り組んでまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q10
町の財政について伺います。ふるさと納税、企業版ふるさと納税ともに税収が伸びています。
人口 減少のなか、独自財源の拡大は明るい報せです。財政の将来見通しをどのようにお考えですか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
私たちの住む町が「小さくても輝く吉見町」「田舎でも誇れる吉見町」となるよう
「未来を引き継ぎたい」と思えるまちづくりとして、ふるさと納税や企業版ふるさと納税による寄附、大和田地区の産業団地整備など、
自主財源の確保につながる取組を進めています。
特に、ふるさと納税については、返礼品の拡充や新たなポータルサイトへの出店など積極的な寄附金獲得の取組を行い、
全国各地から多くの応援をいただき、令和4年度には、2億円を超える寄附額となるなど成果が表れています。
また、産業団地の整備に伴う企業進出により、固定資産税等の税収増が期待されています。
固定資産税は、町の財政を支える安定的な財源であるので、今後においても積極的な企業誘致の取組を進めてまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q11
空き家について伺います。空き家の利活用促進を目標に、町は空き家バンク制度を昨年開設しました。
町で今後も増える空き家にどのように取り組む考えですか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
町では、空き家を住宅として使う場合においても、住むことができる方が限定されるなど、
法規制により自由な利活用ができない物件があります。
現在、定住化促進奨励金、住宅リフォーム補助金などの支援制度を策定するとともに、
町の実情を踏まえた利活用の推進や適切に空き家の情報をお伝えしていくため、
宅地建物取引業協会と連携し空き家バンクを設置しています。
また、令和6年度には、新たな空き家を発生させない取組を始めた自治会もありますので、
所有者や相続人の意向を尊重しながら、地域と行政が協力して空き家対策に取り組んでまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q12
フレンドシップハイツよしみの再生について伺います。温泉事業と野球事業を運営する企業が同施設の再オープンに現在取り組んでおり、
町への経済波及を期待する声もあります。観光振興にどのように取り組む考えですか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
町には、道の駅、国指定史跡である吉見百穴、豊かな自然やイチゴなどの地域資源があることに加え、
関越道や圏央道からのアクセスも良いことから、多くの来訪者をお迎えしています。
しかし、町を訪れた方は、滞在時間の短い観光が大多数を占めており、
経済的な波及・相乗効果と交流人口・関係人口の拡大が課題となっています。
フレンドシップ・ハイツよしみは、町内唯一の宿泊施設であり、本町を訪れてもらう「交流人口」と、
継続的に関係性を持つ「関係人口」をこれまで以上に拡充するための重要な施設となります。
施設の運営には、民間の経営ノウハウや活力を導入し、
時代のニーズに合致した話題性を持たせ、近年高まりつつある、農業体験、自然体験、
スポーツ等の地域資源を活かした滞在型・交流型観光の需要を拡充したいと考えています。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q13
米づくりについて伺います。農業、とくに米づくりの後継者不足が叫ばれています。
どのように取り組む考えですか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
農業従事者の後継者不足や高齢化は、吉見町のみならず全国的な課題であります。
特に米づくりおいては、天候や病害虫など様々な要因により米の収量や価格が左右されること、
そのほか高価な農業用機械・設備や近年の農業資機材の高騰もあり、利益が思うように上がらない状況が続いています。
これに加え、効率的な耕作には農地の集積・集約が求められており、米づくりに参入することは容易ではありません。
土地改良区や水利組合など、地域の方々と意見交換をしたなかで、
10年先の地域農業の計画書である「地域計画」というものを東西南北の地区別に作成しました。その計画書において、
現在の耕作者がより効率的な耕作ができるよう耕作環境を整え、地域内外(町内外)からも多様な人材を募り、
就農の相談から営農定着まで関係機関が一体となって、切れ目なく取り組んでいくこととしています。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q14
道の駅いちごの里よしみについて伺います。開設から20年が経過し、施設や子ども遊具の老朽化が目立つようになってきました。
どのように対応していく考えですか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
道の駅いちごの里よしみは、平成17年4月の開設から20年を迎えました。
設備等の経年劣化が見受けられますが、施設の適切な維持管理に努めています。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q15
自治会運営について伺います。区長や民生委員など、自治会運営に欠かせない役割を担ってくださる方が減っています。
地域コミュニティの維持にどのように取り組みますか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
自治会などの地域コミュニティは、福祉活動、防犯対策、災害時などの際には、
欠かすことのできない身近な組織であります。
引き続き、組織を維持するため、区長や民生委員など地域と行政のパイプ役を担っていただいている皆さんと協力しながら、
顔の見える、つながりのある地域づくりに取り組んでまいります。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
Q16
吉見町の魅力はなんだと思いますか?魅力ある町、吉見町で暮らしたい、学びたい、
働きたい、訪れたいと思う人を増やすため、どんな事に取り組みたいですか?
 宮崎 善雄
宮崎 善雄
吉見ならではの自然や田園風景、人と人とのつながり、伝統や文化など町全体で大切にしてきたものが魅力だと思います。
変化の先を見て、あるものを活かし、つなげ、様々なことを試し、「未来へつなぐ みんなで安心して暮らせるまち」の実現に向け、
各種事業に鋭意取り組み、つながりを実感できるコミュニティを形成していきたいと思います。
 神田 隆
神田 隆
回答なし
公式インスタグラムはこちら
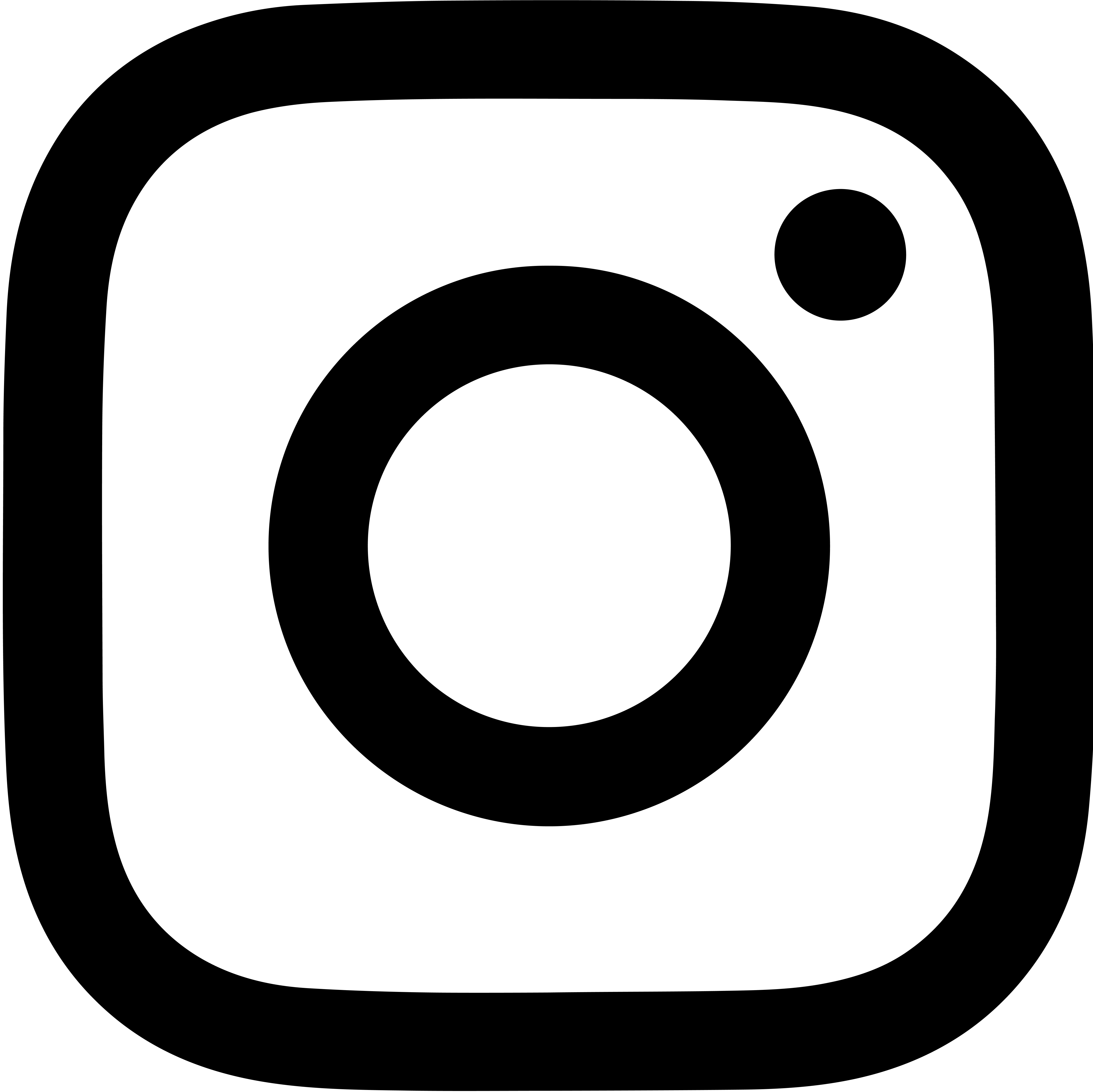
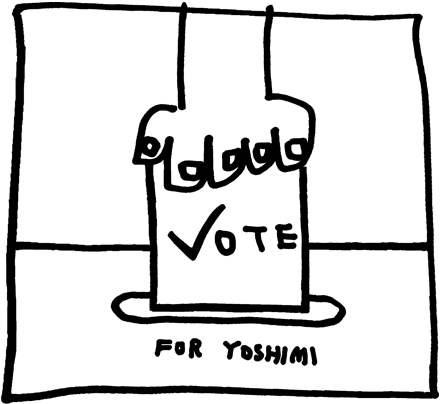
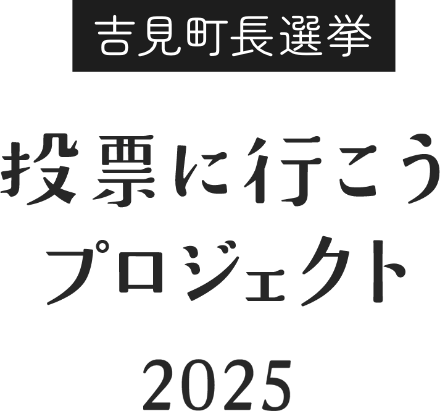
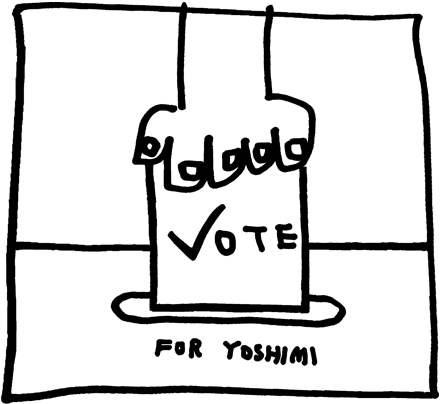
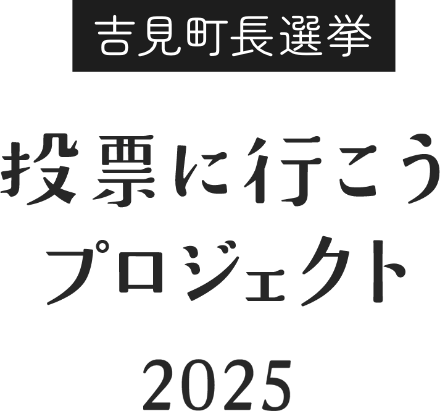
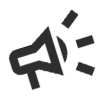 候補者紹介
候補者紹介


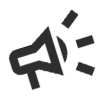 質問と回答
質問と回答